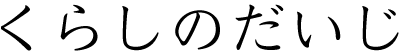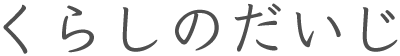梅干しに梅酒、梅シロップ、梅ジャムに梅味噌……
旬の手仕事の代表格ともいえる「梅仕事」の季節がやってきました。
「梅は三毒を断つ」や「梅はその日の難逃れ」などと言われるように、梅は、昔から毒消しの妙薬として注目を浴び、利用されてきました。
この三毒とは、水毒、血液の毒、そして食物の毒の事を指します。
水毒は体内の水分の汚れや滞り、血液の毒は血液の汚れ、食毒は食生活の乱れによって体内のバランスが乱れた状態です。
梅を食べていればこのような毒を消し、健康を保つことができるというわけです。
「身体にいいから」と親や家族に言われ、それとなくいつでも家にある、とても馴染み深い食材である梅干し。
梅仕事は、少ない材料で簡単に始められます。
梅・梅干しの薬膳効能を知り、効果的に健康維持に役立てましょう!
梅の薬膳的効能
薬膳の考え方では、梅は生津作用があるとされ、滞った余分な水分によるトラブルを解消する働きがあります。
五味は酸で、梅の酸味は消化液の分泌を活発にし、消化吸収をスムーズに行うことを助け食欲を増進させます。酸味の招待はクエン酸で、食中毒を起こす菌に対する抗菌力や整腸、解毒の作用があります。
内臓をいたわるはたらきもあるので、夏バテや、疲労回復、胃腸強化にも効果的です。
スーパーなどで手に入る梅は、一般的に生食には向いていません。漬けたり干したりと、加工品にして食されます。
梅は、アミグダリンという青酸配糖体を持っていて、少量だと食べても大きな問題は起きませんが、多量に摂取すると健康障害を起こすケースがあります。果実の成熟や加工により、アミグダリンは分解されて消失していくので、梅干しなどの梅加工品は安全に食べることができます。
「梅干し」の材料は、梅と塩と赤紫蘇です。
梅に、塩と赤紫蘇の薬効が加わることで梅の薬効が増して相乗効果を得られ、保存性が高められます。
美味しい梅の選び方

梅を選ぶ際には、表面に傷がなく、形が丸くふっくらと整っていて、果肉が厚く粒がそろっているものを選びます。
表面に傷や虫食い、斑点などがあると、加工してもきれいに仕上がらず、苦みやにごりの原因になるだけでなく、カビや腐敗の原因となるもなるので避けましょう。
用途の違いによって、粒の大きさや熟成度合いを使い分けるのが一般的です。
青々として硬い実は、梅酒や梅ジュースに適しています。
黄色く色づいて、甘い香りが漂ってきた黄熟梅は、梅干しに。熟成が進んだものは果肉がやぶけやすいので、梅ジャムにするのがおすすめです。
梅干しの作り方
梅干しには、果肉が厚く、熟しかけた黄色っぽい梅が適しています。
本レシピは、塩分濃度13%ですが、塩分が気になるな~という方は、塩の量を10%にしても問題なく漬けられます。
《材料》
梅 1㎏
塩 130g(今回は塩分濃度13%)
ホワイトリカー 適量(200㏄あれば十分)
赤紫蘇 200~300g(梅の量に対して20~30%)
塩 20gほど
《道具》
竹串orつまようじ
キッチンペーパー
保存容器(本レシピではジッパーのついた保存袋を使用)
《事前準備》
保存容器は、煮沸するかホワイトリカーを回して消毒しておく。
《作り方》
1.梅は、傷をつけないようによく洗い、竹串でヘタの部分をとる。

2.キッチンペーパーで水気をよく拭きとり、ホワイトリカーにくぐらせる。
3.ジッパー袋の中に、2の梅、分量の塩を交互に入れ、梅酢が上がるまで冷暗所で漬ける。(1~2週間)

※梅酢が上がるまで2・3日に一度は、ジッパー袋を軽く振ってまんべんなく塩もしくは梅酢を回すようにすると、カビ防止になりますよ。
~赤紫蘇をもむ~
4.赤紫蘇の葉だけを取りよく洗って水気をきる。

5.分量の半分の塩を4に振り、よくもみ、しっかりと汁気を絞って汁を捨てる。同様にもう一度くり返す。
6.3のジッパー袋の中に5のもみ紫蘇を入れて馴染ませ、冷暗所で保管する。

7.土用の頃(7月10日頃)まで漬けたら、天気がいい日の続きそうな日を選び、梅酢から梅と赤紫蘇を引き上げ、3日ほど表裏かえしながら天日に干す。

干して乾燥させた赤紫蘇は、細かく刻むかプロセッサーにかけると簡単に“自家製ゆかり”の出来上がり。
ジッパー袋に残った梅酢は、半日ほど干した新ショウガを漬けると、“紅しょうが”が出来ます。
梅干し作りの副産物である、赤紫蘇と梅酢も、調味料としても大活躍しますので有効活用してくださいね。


食材情報
梅 … 性味:酸・平 帰経: 肝・脾・肺・大腸
紫蘇 … 性味:辛・温 帰経:肺・脾 ※効能は赤紫蘇の方が高い
塩 … 性味:鹹・寒 帰経:胃・腎・大小腸